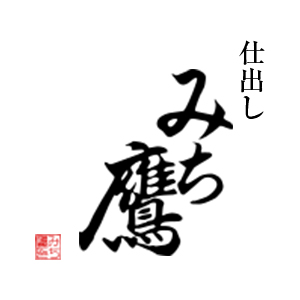コラムCOLUMN
春になり、陽気が高まりはじめたことにより、外では草木が新たに芽を吹き、虫や動物たちも活発に動きはじめるように、同じ自然の中で生きている、私たち人間もまた、だんだんと活動的になり、気分も高ぶりやすくなってきます。
そのため、春は、なかなか上手く眠れずに、睡眠に関する悩みを抱える人たちが増えてくる季節でもあります。
この時期、そうした眠れない人たちのために、病院ではよく睡眠薬が処方されていますし、薬局では、手軽に手に入れることができる睡眠改善薬や、睡眠に特化したサプリなどがよく売れています。
しかしながら、この睡眠薬や睡眠改善薬などは、どうしても寝たい時に上手く頓服的に使うのにはよいのですが、日頃から常用することで、ウトウトしてるのに頭は冴え、少しの物音でも目が覚めてしまったり、夜間、トイレに起きた際に転んでしまったり、日中に、眠気やだるさ、集中力の低下などが起きてしまったりと、副作用や、依存性のリスクが大いに懸念されてしまいます
また、それらの不眠状態への対処は、一時的なものに過ぎず、決して根本的な眠れない原因に対し、改善を行っていくものではありません。
そんな人それぞれの眠れない体質の改善や、慢性的な不眠の解消には、漢方薬が効果的です。
それぞれの不眠の原因に合わせた漢方薬の活用
眠りを妨げる様々な原因については、以前にも一度、考察してみた記事をこのコラムの中に書いておりますので、ぜひ読んでみて下さい。
《2021年7月26日 投稿》 『眠りたいのに眠れない。その原因はどこにある?』
https://www.ohga-ph.com/column/detail/?cms_id=378&people=1
では実際に、それぞれの睡眠を妨げる原因に対し、どんな漢方薬がよいのでしょうか?
薬局の店頭に並んでいる漢方薬の表書きや、病院で処方された時の添付文書だけでは、やや分かりづらい部分もありますので、ここで改めて、その使い分けとなる例を、いくつか簡単にあげてみたいと思います。
漢方薬を使われる際の、一つのヒントになれば幸いです。
◆『ストレスやイライラ、考えごとなど、精神的な要因がある』
やはり、この部分が、不眠の原因の中ではもっとも多いものと思われます。
横になってから一つのことを考え出すと、なかなか寝付けなくなり、胸苦しくて動悸も感じ、体勢が落ち着かない時には「柴胡加竜骨牡蛎湯」、特にイライラや怒りがおさまらない時には「抑肝散加陳皮半夏」、加えて、トイレにもよく起きるようであれば「竜胆瀉肝湯」などが効果的です。
また、やや神経過敏で小さなことでも気になって、常に不安で落ち着かず、眠れないタイプの人には「桂枝加竜骨牡蛎湯」がよいでしょう。
よく、柴胡加竜骨牡蛎湯と桂枝加竜骨牡蛎湯を、やや体力がある方と虚弱な方で、使い分けることもあるようですが、使う期間や、生薬一つ一つの薬効とその組み合わせを考えると、必ずしもその限りではないと思われます。
双方に含まれている竜骨と牡蛎には、「重鎮安神薬」と言われている、高ぶっている気持ちをスーッとおろし、落ち着かせてくれる働きがあります。
◆『過労や慢性病、加齢などによる滋養物質の不足』
人は、過労が続いたり、病気が長引き虚弱になったり、加齢が進んだりすることにより、体を疲労から回復させて、しっかり眠らせるための、「滋養(体内の栄養)物質」が減少しがちになってしまいます。
そのため、眠りが浅い、何度も目が覚める、よく夢をみる、起床時に疲れが取れないなどの症状があらわれだし、気分も落ち込みやくなります。
このタイプの不眠には、体に不足した血や栄養物質を補い、心身を安定させてくれる「帰脾湯」や「加味帰脾湯」が効果的です。
さらに進んで、疲れ過ぎて気が高ぶりなかなかな眠れない人には「酸棗仁湯」、手のひらや足の裏がほてり、動悸や口渇があるようなら「天王補心丸」などが、よいかと思われます。
◆『生活のリズムの乱れ』
夜勤の仕事や、夜ふかしが続き、生活のリズムが乱れて起こる不眠には、体質や状況により様々な漢方を使う場合もありますが、処方に迷う時、まずは体における夜と日中のバランス、いわゆる、漢方でいうところの陰と陽の調和を促す処方の、「桂枝加竜骨牡蛎湯」から服用をはじめてみるとよいでしょう。合わせて環境も少しずつ改善できればなお良いです。
◆『ホルモンバランスの乱れ』
特に女性の場合は、更年期や生理前のPMSなどによるホルモンバランスの乱れで、神経も興奮状態になりやすく、不眠の症状が起こりやすくなります。
この場合は、不足しがちな血を補い、高ぶりやすくなった気を巡らせて、ホルモンバランスを整えてくれる「加味逍遥散」や「抑肝散加芍薬黄連」が、また、冷えやすく、口が乾き、手足がほてりやすければ「温経湯」、さらに、寝汗などが目立ち、軟便気味であれば「柴胡桂枝乾姜湯」といった処方が適しているとして考えられます。
◆『飲食物の不摂生』
これもまた、眠れない原因の1つとして、かなり多くの人に当てはまるものと思われます。
日頃から、脂っこい物や濃い味の物をよくとる人や、お酒をよく飲む人は、胃や消化器系で生じた熱が上昇し、口の苦みや不眠などを起こしやすくなりますし、夜遅い時間や、寝る前に食事をしがちな人は、胃に残っている物の消化活動が、終わらぬままに横になっているため、よく眠れなくなります。
その上、こうした飲食物の不摂生が原因となって、胃の調子を整える自律神経のバランスも乱れがちになり、夜に体をリラックスさせる副交感神経が十分に高まらず、なかなか寝つけない状況も起こりやすくなってしまいます。
また中には、食べたらすぐ眠くなってしまうという人もいますが、仮にそのまま寝落ちすることがあっても、その眠りは浅く、寝覚めには疲労感や胃もたれが残ることも多いでしょう。
この飲食物の不摂生からくる不眠には、消化を助けながら胃腸の機能を回復し、自律神経を整え、睡眠の質を高めてくれる生薬を組み合わせた「加味温胆湯」や「温胆湯」、あるいは胃の内容物の消化を中心に考えて、「半夏瀉心湯」や「六君子湯」、さらには、「安中散」や「胃苓湯」といった処方が、その候補としてあげられるでしょう。
◆『その他の原因からくる不眠』
さらにもう少しだけ、手短に例をあげるとしたら、冷えが強くて眠れない時には「麻黄附子細辛湯」や「真武湯」や「人参湯」、また、足の裏のほてりがひどく眠れない時には「三物黄芩湯」、加えて、眠れないことに焦りを感じ落ち着かず、のぼせや乾燥感があれば「黄連阿膠湯」なども、不眠の原因に対する処方として、よく使われています。
その他にも、不眠の原因とその漢方薬に関しては、ここでは書ききれないほどの、たくさんの事例があります。

上手に使って眠れる体へと変えていく
漢方薬は病院の睡眠薬とは違い、脳や体に対し直接的に、あるいは半ば強制的に眠らせようとするものではないので、飲んだからといって、すぐに、よく眠れるわけではありません。
漢方薬は、ただその時だけ、しっかりと眠れるようにするのではなく、多少の環境や季節の影響を受けながらも、一人一人の体質に合わせ、眠れない原因の改善に働きかけて、自然な形で眠りへと向かわせてくれる薬です。
もし、活用を検討する上で、上記のような使い分けを参考にしてみても、あれこれ当てはまり迷うようであれば、優先順位の高い原因から考えて漢方を選んでみたり、専門家のいるところにしっかり相談して、自分に合った不眠の処方を選んでもらうとよいでしょう。
慢性的な不眠でお悩みの方は、ぜひ、漢方薬を上手に取り入れながら、睡眠薬に依存しない、眠れる体づくりに取り組んで頂ければ幸いです。
★カウンセリングについて★
気になる症状の改善や緩和に適した、漢方薬や健康食品を、きちんとセレクトするために、カウンセリングにはしっかりと時間をかけて対応させて頂きます。
さらに症状の根本的な原因となる部分を認識するために、陰陽五行体質判定システム(税込1,000円)の活用による漢方カウンセリングも、ご希望に応じて行っております。
あなたのこれからの過ごし方が変わってくるかもしれません。
詳しくは下記の「漢方薬相談」の画面をタッチして、予約内容を一度のぞいてみて下さい。
(※ネット予約に限らず、お電話でも、気軽にご予約下さいませ! TEL 092-733-7231)
⇓

福岡市中央区天神2丁目11-3 ソラリアステージビルM2F(中2階)
TEL 092-733-7231
(株) 大賀薬局ライフストリーム 漢方カウンセリング (担当) 梅川

ご相談は私までお声がけください!
梅川 哲朗 (登録販売者・九州中医薬研究会会員・国際中医臨床薬膳師)
所属店舗 ライフストリーム
ご相談の際は、店舗宛TEL092-733-7231までご連絡ください。
⇒店舗の詳細はこちら
色んな症状を持ちながら診療では病気ではないと言われて悩むお客様方にお役に立ちたく、日々、中医薬診断の学びと実践に努めています。細かい症状などを伺って体質を判定し、お客様個々に合った漢方薬や市販薬の上手な活用法をご提案しております。お気軽にご相談下さいませ。
あわせて読みたい関連記事
書き手
バックナンバー
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
お問い合わせCONTACT
-
メールでのお問い合わせはこちら
【お客様専用】お問い合わせフォーム -
緊急時、お急ぎの方はこちらから[24時間対応]
24時間お薬相談 -
皆様からよくいただくご質問です。
よくあるご質問 -
法人のお客様はこちらからお問い合わせください。
法人様向けお問い合わせフォーム


 0
0
 1
1